You've got mail #12
「星の王子さま」からの手紙
2014年3月21日(金) 開演 午後6時30分
2014年3月22日(土) 開演 午後2時
北区滝野川会館・大ホール
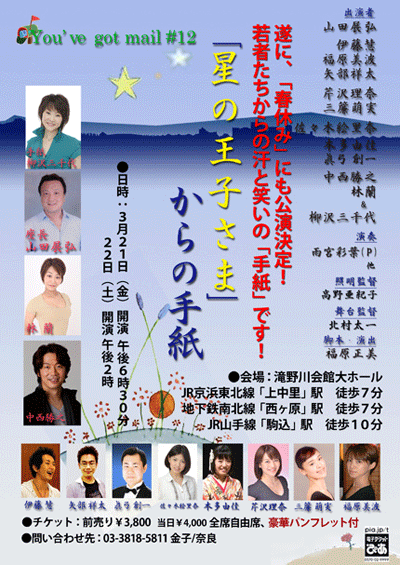
<演奏曲目>
第一幕
・ 花は咲く
・ 鉄道唱歌
・ 星の界
・ 明日へのマーチ
・ せんせい
・ さよならの向こう側
・ 初めての出来事
・ 春夏秋冬
・ 川の流れのように
第二幕
・ 六甲おろし
・ ビリーブ
・ さくら
・ 明日があるさ
ピアノBGM
・ 早春賦
・ クレメンタイン
・ 祭り
・ クレメンタイン
・ カノン
<演出・脚本 福原正美>
この公演が始まって今年は12年目。
12年、といえば、古代東洋の生活習慣なら干支が一巡しますので、天地の神々に大袈裟なお祝いをするところなんでしょうが、ね。
「神々のお陰でこんなに生き続けられました。感謝で~す!」舞台演劇と万(よろず)の神々との関係はものすごく古すぎて、人がこの地上に出現したときからその関係は続いていたのではないかと思えてきます。やれ田植えだ、引っ越しだ、子が誕生した、七五三だ、結婚だ、稲刈りだ、春が来る、実りの秋が来るなどなど、社会生活の節目節目でその日を担当する神々が登場して、その都度、巫女たちによる「舞踏」が大衆に披露されて、王家も大衆庶民もこの日ばかりはひとつになって、巫女の「舞踏」に拍手をおくっていたようです。要するに古代人は舞台演劇を生活に溶け込ませていたのです。漢字文化を共通に持つ国家なら、この長い長い生活習慣をそう容易く消し去ることは出来ません。この名残りでおもしろいのは、お相撲の「房」です。
方角を、「青、赤、白、黒」の色房にして「東、南、西、北」を表し、季節の「春夏秋冬」も方角にあわせて、「青春、赤夏、白秋、黒冬」としています。最新の技術を踏襲した現代建築の舞台でも、とくに「国立…劇場」ではそうなのですが、役者たちが舞台に上がるまでの廊下の途中、上の方にぽつんとちいさな「お社」が奉られています。これは明らかに、古代生活習慣の名残なんですよ…。でもね、こんな古くさい話なんぞ知らない役者さんたちが大勢いるのもまた、現代の舞台演劇の世界なのです。おもしろいことです…、ハイ。
巫女さんは引っ込み思案、恥ずかしがり屋でもありません。どちらかと言えば、人前で披露出来る「技」を天から授り、それを平気で人前で披露できる人です。その「技」は、大勢いる人の中で特別に輝き、喜ばれました。笑いが生まれ、人々の涙を誘い、人々に感動を誘い、素朴に生きる人たちに神秘的に感じる「想像の世界」を見てたのです…。そう、人の心の中にある「神々の世界」を見せてくれた人が、巫女さんだったのです。神々と人々の架け橋役をしていたのですから、「特殊な能力」をもっている人にはちがいありません。
古代の巫女たちはいま、テレビの役者やタレントさん、歌手に魔術師、漫才漫談、浪曲に歌謡曲の歌い手、日舞に歌舞伎、モダンダンス、バレエ舞踏家、そして舞台役者に映画俳優たちに姿を変えてボクたちの現実世界のなかで「特殊な能力」を披露しています。作家や詩人、楽器演奏家に作曲家なんてのも、おなじ世界の人たちです。これらすべての人々が、この世から消えても私たちは生活出来ます。パンは残っているのですから。でも味気ないでしょう、こんな世界は。この人たちがいなくなったら、「想像の世界」が消えてしまいます。
古事記に登場する「天宇受賣命(アメノウズメ/日本書紀では天鈿女命)」から幾代の時が流れ、その時の流れの中でボクは東京・渋谷で生まれました。小学生時代から東映とパンテオンで週末を過ごし、恋文横町を駆けずりまわり、ジャズ喫茶でたばこの香りを覚え、日本大学芸術学部文芸学科創作コースに進学しました。まあ、もっともこの学校しか行くところがありませんでしたが…。
そしてまた時が流れ、国立音楽大学声楽科卒業の岡田誠君と出会いました。ふたりで、「コンサートでも、すっか?!」と意気投合。「また来年も!」ってことから「ユーガットメール」が続いてきました。
ボクは今の学生たちが言う「日芸」で、岡田君は「クニオ」。二人で始めたので、この舞台にはどうしても「日芸君とクニオさん」の出番が多くなります。演劇と音楽のまぜマゼ舞台だから…。
ありったけの音楽と、散在する「ことばの世界」の創作者たちを集めて、八百万の神々が住んでいると古代人が言う「舞台」という特殊エリアを皆様とともに見させていただきます。私たちが生きているこの世界に、ともに感謝しようではありませんか…。
本日は「春分の日」。
情熱だけが取り柄の若者たちの創る「想像の世界」を!時の流れも忘れて、皆様、ご存分にお楽しみください。
